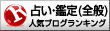郭氏元経の年家独火篇の真実
あの連中の話しは無駄であり、アホ過ぎるので書きません。
郭氏元経巻之四に年家獨火篇という篇があるのですが、ここは干支九星や気学だけで考えると絶対にわからない篇のひとつです。
例えば、この年家獨火篇の中の文で
如戌亥年、用巽卦。冲處、是乾為五鬼獨火之神。餘倣此。
”戌亥ノ年ノ如キ、巽卦ヲ用ユ。冲處、是(コレ)、乾ヲ五鬼獨火之神ト為ス。
餘ハ此ニ倣ヘ。”
という一文がありますが、この文を普通に干支九星や気学の知識で考えますと、
”戌亥の年に巽宮を使う?
歳破方位を使う?
太歳方位を五鬼独火の神とするのかな?”
となり、非常におかしな解釈になってしまいます。
しかしここで、小游翻卦(しょうゆうほんか)や大遊年変卦(だいゆうねんへんか)というものが理解出来ますとこの文で出て来る「巽卦」と言う言葉の意味がわかってきますので、この一文が理解出来てこの篇全体が理解出来る様になります。
実際、私も最初はここの篇は、理解出来ませんでした。
どちらかというと、後戻りして理解し直した感じでしたが、この篇の理解についての具体的理解については、拙著「郭氏元経(解説付)」に任せます。
また、この篇を読み解くヒントは、郭氏元経の巻之八東西篇にもあります。
この東西篇が理解出来ないと、この一文は、理解出来ません。
では、この小游翻卦や大遊年変卦は、一体何を見れば理解出来るのかと言いますと、まずは
「欽定協紀辨方書 36巻」
(著者 清允録等奉勅撰 出版者不明 乾隆6 [1741] 序)
を見る必要があります。
この本は中国清朝時代の本で漢文ですが、この本に出ていますので、この本を見ると理解できます。
そしてこの「欽定協紀辨方書」は、和訳した本も実は出ています。
しかし、その本は、古本でしか入手不可な本ですが、
「人相手相 五體相學圖解 提要協紀辨方書譯解」
(柄澤照覺 史籍出版 昭和57年)
と言う本です。
そして、この小游翻卦や大遊年変卦について出ている日本の本としては、
「洛地準則」(多田鳴鳳 出版社. 岡本偉業館 1926年)
ですので、この本の解説本を見ればわかります。
「洛地準則詳解」という本があります。
ただ、それでも小游翻卦や大遊年変卦についての全貌はわかりませんが、郭氏元経巻之四の年家獨火篇を理解するには、これで充分です。
そうすると、郭氏元経が最初に発刊されたのが1632年で、欽定協紀辨方書が発刊されたのが1741年で、洛地準則が発刊されたのが1926年ですから約100年後、300年後の本を見ることになり、凄く面白いと思いました。
つまり、郭氏元経は、この様に色んな占いの原典的要素を含んでいるということです。
そのため、この本を理解しようと思うと、この様に色々なことを調べて掘り下げなければなりませんので、膨大な資料となる訳です。
そして、郭氏元経の自分勝手な解釈と一部分だけ取り上げて変な方法で使うというのも危ないということがわかります。
郭氏元経→欽定協紀辨方書→洛地準則と繋がると考えると面白いと思いますし、なんかわくわくして来ませんか?
日本の昔の占い師は、本当に良く勉強したんだということが分かりますので、私達も負けてはいられません。
後、これは、私からの注意事項ですが、一部の方が私の郭氏元経の解説本を購入頂き、その内容を自分がわかるところだけを取り出して金銭を受領して生徒さんに教えているそうですが、そういった事を絶対にしないで頂きたいと思います。この本の全体をキチンと理解して頂いた上で教えるのなら何の問題もありませんが、中途半端な解釈では、全く違う間違った方位の使い方をしてしまう可能性もありますので、絶対におやめ下さい。
私の聞いた限りでは実際に間違った解釈をして教えていました。